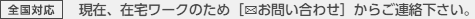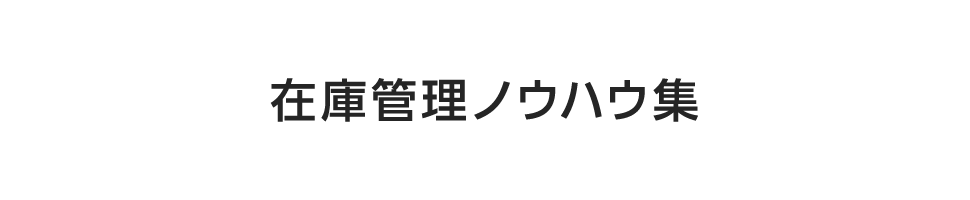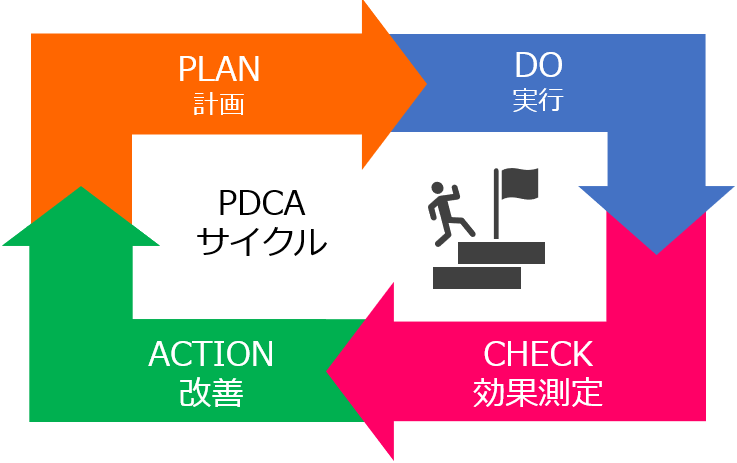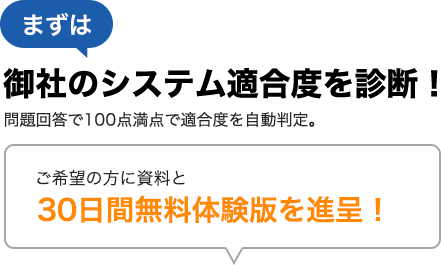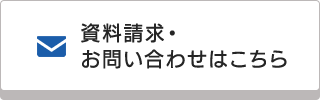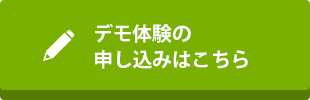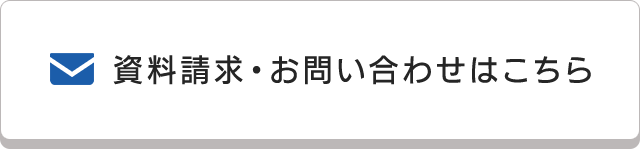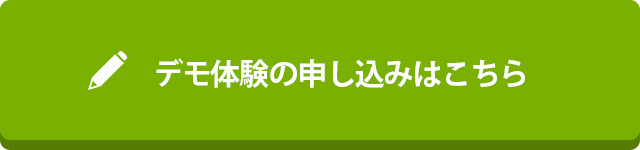今日は「在庫の先入れ先出し」という、この言葉。「現品の入出庫」業務と「財務会計」業務、それぞれで違うものを指してますよ、という話をしたいと思います。
「先入れ先出し」。英語で言うと「Fisrt In First Out(FIFO)」。「ファイフォ」や「フィフォ」と呼ばれることもあります。
物が先に入ってきたものを先に出すという基本の考え方は同じなんですが、現品の入出庫と財務会計だと具体的にやらないといけない作業や処理、これ全く違います。
この2つの違い、どうしても言葉が同じなので、混同されている方をよく見かけます。混同してしまうと、やらなくてもいい管理や作業をやってしまい、時間の無駄やロスが発生してしまうことにもなりかねません。
今日は現品の入出庫と財務会計における在庫の先入れ先出し、この違いについて簡単に解説したいと思います。
現品の入出庫における先入れ先出し
まずは現品の入出庫における先入れ先出しについて解説します。これは非常にイメージしやすいんじゃないかなと思います。文字通り先に入ってきた現品を優先的に出庫します。
その判断の軸として、入荷日やメーカーがつけてくる賞味期限、消費期限といった日付をもとに、どれが一番古い在庫かを確認して、一番古い在庫を出荷していく運用になります。
子供の頃、母親に「古い卵から使いなさいよ」と注意された記憶がある方もいると思います。まさにあれが現品の先入れ先出しです。
- メリット
メリットとしては、自分が持っている在庫、会社の資産の在庫をなるべく新しいものにする。そのことで在庫の廃棄ロスを回避して、無駄なコストをかけないようにします。
食品や医薬品、劣化の早いアイテムを扱う場面では非常に多く採用されている運用です。
- デメリット
一方でデメリットもあります。管理工数、作業工数が上がってしまうという側面です。
例えば、現品を扱う時、前からモノを取った際に、残ったモノを前に詰める作業が発生したり、積み置きしていると上の方が新しい在庫になるので、出庫時にそれを一度避けて古い在庫を出し、また戻すといった作業になります。
さすがに、それだと作業性が悪いということでラックを導入しても、同じアイテムで別の日付のものを同じ棚に入れないようにする、といった工夫が多く見られます。
つまりアイテムごとに日付別で別管理していく運用になります。
システム上も、その軸となる日付情報をデータでしっかり管理しておく必要があります。例えば、棚卸の際も、アイテムごとに日付別で確認し、データを作って登録しなければなりません。
金属のように劣化が少ないアイテムでこれを採用すると、デメリットの方が大きくなる側面があります。ですので、現品の先入れ先出しに関してはアイテムの特性によって選択するのが正しい考え方かなと思います。
いずれにしても、倉庫の部門の方が「在庫の先入れ先出し」とおっしゃる場合は、この現品の先入れ先出しのことを指しています。
財務会計における先入れ先出し
次は財務における先入れ先出しについて解説します。
財務会計は外部に報告するための会計処理です。外部への報告の最たるものは「決算」となります。
決算では企業が持っている在庫を金額で評価して提出しなければなりません。金額評価は勝手なルールでは許されず、あらかじめ決まった評価方法の中から選んで税務署に申請し、その方法で毎年決算を行います。
評価方法には最終仕入原価法、総平均法、個別法などがあります。その中の一つとして「先入先出法」があります。
これは、先に入ってきたものを先に出したと見なして計算する方法です。
例えば、商品Aが期末に100個残っているとします。
- 直近の仕入れ:(1個)50円で80個
- その前の仕入れ:(1個)40円で100個
この場合、
- 100個中の80個は直近仕入れ分:50円×80個=4,000円
- 残り20個はその前の仕入れ分:40円×20個=800円
合計4,800円が期末在庫の評価額となります。
これを全アイテムについて行うのが「先入れ先出し法」です。
ですので、経理の方が「先入れ先出し」と言う場合は、この評価方法のことを指しています。
現品と財務の関係
それでは、財務会計で評価方法として「先入先出法」を採用している場合、現品の入出庫も先入れ先出しで運用しないといけないのでしょうか?
そんなことはありません。アイテムの特性に合わせて実際の入出庫のオペレーションは検討すればいいのです。
例えば、製造業でネジや金属部材のように劣化しないものは、作業性を優先してシステム上ではアイテム別でのシンプルな管理にとどめる。実際の出庫作業では、なるべく先入れ先出しになるようにしてください、程度にとどめておく。
一方、液体の原料のようにメーカーの有効期限が明確なものは、システム上でも有効期限ごとに在庫を別管理して、きっちり先入れ先出しを実現する。
こういう運用で結構です。
まとめますと、在庫の評価方法としての先入れ先出しと、現品の入出庫における先入れ先出しは別問題です。現品の先入れ先出しはアイテムの特性に応じて選択してください。
さいごに
今日は、在庫の評価方法としての先入先出法と、現品の入出庫における先入れ先出しは別問題ですよ、という話しをしました。また、現品の先入れ先出しをシステム管理し、厳密に行うかは、各アイテムの特性に応じて選択してください、という話しもしました。
「このアイテムは判断の軸となる日付別で管理する?しない?」を人の記憶に頼ってやると報告がばらつき、運用統制が効かなくなります。
我々が提供している在庫スイートクラウドでは、アイテム別で日付別管理をする/しないの設定が可能です。しかもCSVを一括アップロードすれば簡単に反映できます。
ぜひ、現品の入出庫の先入れ先出しを検討されている方はお気軽にご相談いただければと思います。